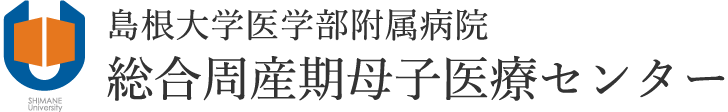センター長挨拶 Greetings

島根大学附属病院総合周産期母子医療センターは、出生率の低下や高齢化といった人口動態の変化、地域間の医療格差など複雑な課題に直面しています。これらのセンターは、妊娠から出産、そして育児支援まで一貫した高度医療を提供することが求められており、特に地方ではその重要性が一層高まっています。こうした背景の中、周産期医療の質の向上を目指して、いくつかの対策が考えられます。
まず、医療スタッフの確保と育成が急務です。特に、地方で産科医や新生児科医の不足が指摘されているため、これらの専門医を育成することが喫緊の課題です。そのために、医学生や研修医に対して周産期医療の大切さと必要性を伝えるとともに、キャリアアップの機会を増やすことや医療環境を改善することで専門医が不安なく継続して診療を行うことができる体制を作っています。また、周産期医療に関わる看護師、薬剤師、理学療法士、臨床工学士、臨床心理士などの多くのメディカルスタッフに対して、専門性の高い研修を行うことでone teamで高度な周産期医療を提供できるよう取り組んでいます。
次に、島根県内の周産期施設との連携は最も重要です。各地域の医療機関だけでなく保健所、行政期間、教育機関、NPOなどと連携し、妊娠中の女性や子育て家庭への継続的な支援を行うことで、島根県内の妊婦さんや赤ちゃんが笑顔で安心して生活できるような医療サービスを提供していきます。
これらの取り組みを通じて、多くの課題に対応し、地域社会に根ざした持続可能な周産期医療体制の構築を目指しています。未来に向けて、周産期の母子の健康を守り、島根県が母子にとって世界で最も幸せに暮らすことができるよう、周産期センター一同、真摯に取り組んで参ります。これからもご指導ご協力のほど、よろしくお願い致します。
島根大学医学部附属病院・総合周産期母子医療センター長
産科婦人科学教授 竹谷 健